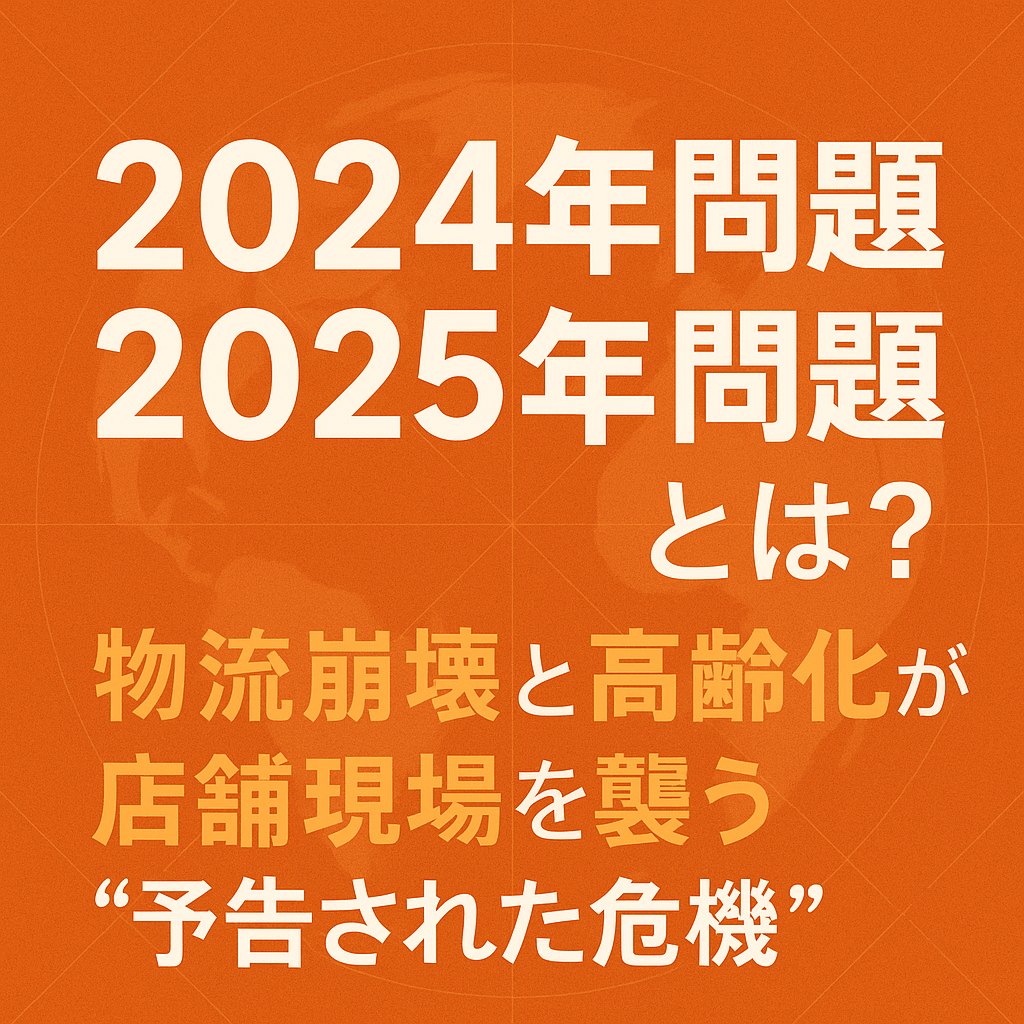【最新記事の目次】
2024年問題・2025年問題とは?|物流崩壊と高齢化が店舗現場を襲う“予告された危機”
こんにちは!森友ゆうきです。
最近、こんなことを感じたことはありませんか?
- 以前より納品が遅れるようになった
- バイト募集しても全然人が集まらない
- 新人がすぐ辞める。教える側の負担が増えている
それ、偶然でも個人の努力不足でもありません。“社会全体の変化”が、あなたの会社や店舗を静かに蝕んでいるのです。
この記事では、いま現場で起きている混乱の正体──「2024年問題」「2025年問題」とは何か? そして、店長として何を知り、どう備えるべきかをわかりやすく解説していきます。
第1章|2024年問題とは?──物流の“限界”がやってくる

2024年4月──それは、トラックドライバーに年間960時間の時間外労働の上限が適用されたタイミングでした。
この規制により、長距離輸送が難しくなり、全国で物流の「遅延」や「輸送力不足」が発生しています。
国土交通省の試算では、2024年には約14%の輸送力が不足するという予測も出されていました。
現場で起きていること
- 納品の遅延(とくに週末明けの月曜・祝日後)
- 販促スケジュールのズレ
- 店舗側の欠品による売上ロス
これらはすべて、「物流の常識」が変わってきているサインです。
これまで“当たり前”だった「当日発注・翌日納品」サイクルが崩れ、「事前に読み、前倒しで動く」力が求められるようになっています。
第2章|2025年問題とは?──後期高齢者2,200万人の社会
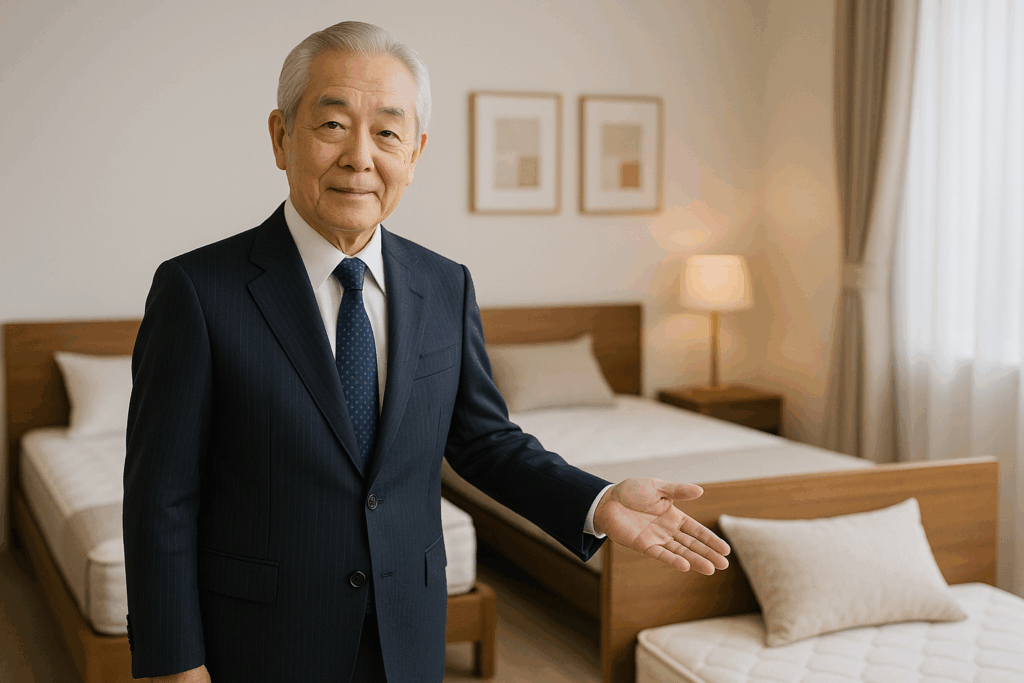
2025年には、団塊の世代(1947〜49年生まれ)が全員75歳を超えます。
つまり、日本人の5人に1人が「後期高齢者」になるという社会です。
どうなるのか?
- 医療・介護サービスが逼迫
- 現役世代の社会保険負担が急増
- 労働人口が大幅に減少
これは、ニュースで語られる“社会保障制度の危機”という話だけではありません。
私たちの店舗運営にも、「人が来ない」「人が辞める」「高齢スタッフが増える」という形で直結しています。
店長にとっての2025年問題
- 若年層の採用難と高齢スタッフのマネジメント課題
- お客様層の高齢化による売場や接客の再設計
- 働きながら介護するスタッフが増加
つまり、「人がいない」だけでなく、「働き続けることが難しい」人が増えていく時代が、すぐそこに来ているということです。
第3章|それ、ずっと前から言われていた──“予告されていた危機”が現場に届かない理由
この2024年問題も、2025年問題も、数年前から国や業界団体で話題にされてきた話です。
- 2024年問題:2018年「働き方改革関連法」成立→2024年施行
- 2025年問題:2012年「地域包括ケアシステム」構想→2025年を目標に高齢化対策
第4章|店舗運営にどう影響し、店長に何ができるのか?
2024年問題・2025年問題は、「国が困る話」ではなく、あなたの店で“すでに始まっている話”です。
現場ではこんなことが起きています。
- 納品遅延:週末チラシ掲載商品の納品が間に合わない
- 販促ズレ:POPや特売と現物のタイミングが合わない
- 採用難:バイト応募がほぼゼロ。来ても続かない
- 定着の困難:「教えきる前に辞める」新人が増えている
これらはすべて、“個人・個店の問題”ではなく構造の問題です。
「もっと頑張ろう」「慣れてもらおう」では通用しない時代に入っています。
では、店長には何ができるのか?
未来を正確に読むことはできなくても、「もう始まっている変化」に備えることはできます。
店長として、今日からできる小さな一手
- 販促スケジュールを「ズレても崩れない設計」に見直す
- シニア・外国人・スキマ人材など、多様な人材活用の仕組みづくり
- 売場や接客を、高齢化した顧客層に合わせて再設計
変化に“気づいて動ける人”が、これからの現場を守るリーダーです。
今できる小さな改善が、未来の大きな安心につながります。
第5章|2024・2025年問題は“通過点”──次に来る「○○年問題」を先読みする

いま私たちが直面している2024年問題(物流)や2025年問題(高齢化)は、実は「序章」にすぎません。
この先も、人口動態や地域構造の変化によって、次々と“○○年問題”が押し寄せてくると予測されています。
では、店舗運営や人材戦略に直結する未来の年問題とは、どのようなものなのでしょうか?
未来年表|これから店舗現場に起きる“〇〇年問題”
| 年 | 問題名 | 店舗現場への影響 |
|---|---|---|
| 2030年 | 地方消滅問題 | 商圏人口が激減し、店を出す場所・人が集まる場所がなくなる |
| 2035年 | 団塊ジュニア高齢化 | 中堅層が一斉に定年退職、「教える人がいない」現象が起きる |
| 2040年 | 社会保障ピーク | 働く人が減る・働き続けられない人が増える・採用競争が激化 |
2030年問題|地方の店舗が“誰にも支えられなくなる”時代
少子高齢化の進行により、地方自治体の多くが「消滅可能性都市」とされる2030年。
商圏人口は減少し、お客様もスタッフも集まりにくくなり、公共交通も維持できなくなります。
つまり、店を「出す場所」がなくなり、来る人・働く人もいない──それが2030年問題です。
2035年問題|団塊ジュニアが高齢者に──“中堅世代”が一気に抜ける構造変化
1971〜74年生まれの団塊ジュニアが65歳を迎えるのが2035年。
これまで主力を担ってきた中堅層が一斉に定年・退職へと向かい、現場から「教える人」がごっそりいなくなる構造変化が起こります。
しかも、次の若い世代が少ないため、「教わる人がいない」状態が続くのです。
2040年問題|すべての“限界”が一気に押し寄せる年
2040年には、後期高齢者が約2,800万人に達し、医療・介護・年金といった社会保障制度が限界に。
家庭での介護負担が増し、「働ける人」が減るだけでなく、「働き続けられない人」も増えていきます。
さらに、労働人口の急減により、採用競争が過熱。今の“採れる前提の人材戦略”は完全に通用しなくなる時代です。
未来は、誰にも止められません。
でも、「知っていた」「準備していた」かどうかは、店の未来を大きく左右します。
店長として、“未来を読む力”を持ち続けましょう。
第6章|まとめ:変化を味方につける“構え”を持つ
2024年問題・2025年問題──それは、突然の出来事ではありませんでした。
ずっと前からわかっていた未来。
では、この先の2030年、2035年、2040年問題に、どう備えればよいのでしょうか?
新聞やニュースを“広く”見ること
制度の変化、人口構造、物流、地域課題…。
一見“遠く感じる話題”も、数年後には店舗現場に確実に影響を及ぼします。
「これ、うちの店にどう関係あるかな?」と、自分の現場に置き換えて考える癖をつけましょう。
社会課題を「自分の責任で対処すること」として考えると、見える景色が変わります。
責任を持つ人だけが、未来に手を打てる人になる。
視野を広く、視座を高く持つ
現場だけを見るのではなく、業界全体・社会全体を俯瞰する視点を持つこと。
それが「なんとなく不安」「なんか違和感ある」を言語化し、行動に変える力になります。
視野を広く、視座を高く。
それは“知る力”の先にある、リーダーとしての構えです。
今回は、「2024年問題」「2025年問題」とは何か? そして、店長として何を知り、どう備えるべきかについて解説しました。
あなたの明日がより良い一日になりますように。
森友ゆうき