【最新記事の目次】
店舗マネジャーの役割とは?店長に求められる現場力と実践スキル
こんにちは!森友ゆうきです。
「なんで私ばっかり忙しいの?」「伝えたはずなのに、なんでやってないの?」
店舗マネジャー、つまり“店長”として働くなかで、こんな言葉を飲み込んだことはありませんか?
店の売上も、人の成長も、クレーム対応も、全部が自分の肩に乗っている――そんな責任感とプレッシャーを抱えながら、現場に立ち続けている皆さんに、今回は「6つの力」を軸に店長の役割を整理してみたいと思います。
第1章|【売上をつくる力】数字を“現場で動かす”マネジメント
売上=客数 × 客単価。この構造はシンプルですが、実際に数字を動かすのは容易ではありません。
たとえば、「今日は雨だから客数が少ないだろう」と察して、入口の販促を切り替える。雨の日用の提案POPを出して、傘やタオルを入口に展開する。そういった機転が売上を動かします。
また客単価についても、「高い商品は売れない」ではなく、「高い商品ほど満足度が高く、リピートに繋がる」という事実を知ることが重要です。
高機能ドライヤーを買ったお客様が「やっぱりいいものは違うね」と笑顔でリピート来店したように、納得感ある提案こそが客単価向上のカギ。
- 「選ばれている人気商品です」と伝える(社会的証明)
- 使用シーンを想像させる(生活価値提案)
- 「こちらとこちら、どちらが良さそうですか?」とダブルバインドで誘導
店長の役割は、販売の“再現性”を設計し、スタッフが同じ成果を出せるよう導くこと。属人的な「売れる人」ではなく、“売れる仕組み”を作る人がマネジャーなのです。
関連記事:高単価品を買うお客様ほどリピーターになる接客術

店長・販売スタッフ・接客のプロのために、最先端心理学をベースとした高単価商品の販売心理を、実例つきで徹底解説します。
関連記事:店舗売上をアップさせるための数字の基本

「売上がなかなか伸びない…」「どこに手を打てばいいのかわからない」
そんな悩みを抱える店舗マネージャーのために、売上を構成する“数字の公式”と、その使い方をわかりやすく解説します。
売上アップはこの公式で決まる!買上客数・買上率・入店客数の基本と実践例
第2章|【育てる力】スタッフが自ら動く職場をつくる
「教えたのに、また同じミス…」そんな経験、店長なら一度や二度ではないはずです。
でも、教えているだけでは育ちません。人が動くのは、「納得」と「成功体験」があるときです。
たとえば、1on1面談で「昨日、自分で工夫したことってある?」と聞いてみると、意外に本人が自分の努力に気づいていないことがあります。
それを一緒に言語化してあげることで、仕事が「評価されるもの」に変わり、行動が強化されるのです。
また、“褒めどころ”を見つけるのも育成の力。「ありがとう、助かったよ」の一言が、次の一歩を後押しします。
育てる力とは、教える技術ではなく“変化を引き出す観察力”です。
関連記事:現場で私が最も活用してきた心理学フレーム

「部下のやる気が見えない」
「褒めても反応が薄い」
そんな悩みを持つ店長さんへ。実はそれ、承認が足りないのではなく、順番が間違っているのかもしれません。
店舗育成の現場で私が最も活用してきた心理学フレーム、マズローの欲求5段階説を使って、「やる気が出ない部下」にどう育てていくかを解説します。
第3章|【仕組みで回す力】属人化を防ぎ、誰でもできるを実現
「◯◯さんじゃないとできない」「あの人がいないと回らない」――そんな属人状態が続くと、現場は不安定になります。
店長としてやるべきは、作業を仕組みに変えることです。その基本構造が「道具→動作→手順」。
- 道具=何を使う?(例:掃除道具、発注端末)
- 動作=どう動かす?(例:押す・拭く・入力する)
- 手順=どの順番で?(例:締め作業→集計→送信)
この3階層で書き出すと、スタッフ間の理解度差が埋まり、誰でもできる作業になります。
仕組みで回すとは、「人を責めずに改善する仕掛け」をつくることなのです。
関連記事:「楽良早安」で見直す店舗作業の基本
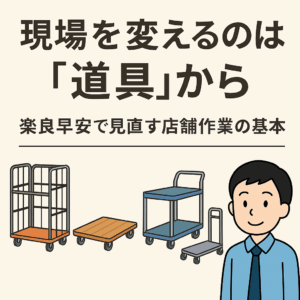
私が現場改善の基本にしているのが、「楽良早安(らく・りょう・そう・あん)」という4つの視点です。
- 楽(らく):身体に無理がなく、ストレスが少ない
- 良(りょう):作業ミスが起きにくく、品質が安定する
- 早(そう):動きに迷いがなく、スピード感がある
- 安(あん):コストや労力を抑え、継続しやすい
この4つの観点から見直すだけで、現場の空気がガラッと変わることがあります。
第4章|売れる売場づくりと店舗レイアウト設計
レイアウトや配色などの“売場づくり”は、無言の接客です。
たとえば、色相環を意識した陳列、回遊導線の設計、視線の流れに合わせたPOP配置など、購買行動に基づいた空間設計が求められます。
補色の力を活かすと、売場の印象が一気に変わる
色相環で反対側に位置する色同士を「補色」と呼びます。
たとえば、赤と緑/青とオレンジ/黄と紫などが補色関係にあります。
補色同士はお互いを最も強く目立たせる性質があり、売場では次のように活用できます:
- 青い棚 × オレンジPOP → 視認性抜群で注目を集めやすい
- 商品と背景の補色づかい → 商品が浮き立つように見える
- 補色を少しトーンダウンして使う → 目立ちつつも落ち着いた印象に
補色を使う際のポイントは、「すべてに使わないこと」。あくまで“見せたい場所”に絞って使うことで、視線の集中と回遊が両立できます。
IKEAやユニクロのように、導線と色設計に戦略がある店舗は、リピート率も高いです。
店舗は接客以上に「空間で語る」。陳列、照明、音、香り、導線――すべてが売場の“無言のセールストーク”。
店長は空間を設計する“演出家”でもあるのです。
関連記事:アメリカ小売業に学ぶ店舗の配色戦略

「このお店、なんか落ち着くな…」「あの売場は、なぜか買いたくなる」
その感覚、実は“色”がつくっているかもしれません。色相環という色彩理論をもとに、ウォルマートとターゲットの店舗戦略を読み解いていきます。
なぜウォルマートは“青”?なぜターゲットは“赤”?色相環・配色に隠れた心理戦略
第5章|【知る力】現場の“違和感”に気づく観察眼
「売上が落ちてる」「ミスが増えた」――その背景にある小さな変化を、どれだけ拾えるか。
たとえば、いつも元気なスタッフが口数少ない。客数は変わらないのに買上点数が減っている。こうした違和感は、マネジャーにしか見えない“兆し”です。
知る力とは、“観察→分析→判断”のサイクルを回す力。
ベテランが感覚でやっていたことを、若手も再現できるようにするには、これを言語化することが不可欠です。
気づける店長は、現場に安心を生みます。
第6章|【防ぐ力】トラブル・離職・クレームを未然に止める
「問題は、起きてからでは遅い」――防ぐ力とは、未来に起こるトラブルを“起きないように”する力です。
たとえば、挨拶が減った、ミスが増えた、報連相が減った。それはスタッフが「やめたい」と心で叫びはじめたサインかもしれません。
私が店長時代、辞めそうなスタッフの“兆候リスト”を作り、週次でチェックしていました。すると、面談のタイミングも、任せる仕事も、変わりました。
また、クレーム対応でも初動を間違えるとSNSに拡散されます。まずは共感→事実確認→改善策の順番を徹底。
防ぐとは、トラブルを事前に設計で“潰しておく”ことなのです。
関連記事:クレーム対応|顧客満足度を上げる3つのコツ

- 「傾聴・共感・スピード」が顧客満足度を上げる鍵
- 悪質クレーマーには冷静・毅然とした対応でブレない軸を
- クレームは“現場力”を高めるヒント。活かすも殺すも店長次第
クレーム対応の極意|顧客満足度を上げる3つのコツ+悪質クレーマー撃退法
まとめ|マネジャーは「現場の未来をつくる人」
店舗マネジャーの仕事は、「現場を回す」ことではなく、「現場を育てる」こと。
6つの力――売上・育成・仕組み・売場・観察・防御――これらを日々の判断軸に持てるかが、現場の安定と成長を決めます。
今日のあなたの“気づきと声かけ”が、明日の売上とチームの笑顔につながります。
現場の最前線で戦うすべての店長に、敬意を込めて。
オススメ記事:森友流 スタッフ育成マスタリーモデル
店舗スタッフ育成にある様々な問題、そんな悩みにバッチリと”フィット”する成長レベルに応じた“関わりの「型」”スタッフ育成マスタリーモデルを公開します!
全5作、ダウンロード可能な小冊子も無料でお付けしています!







