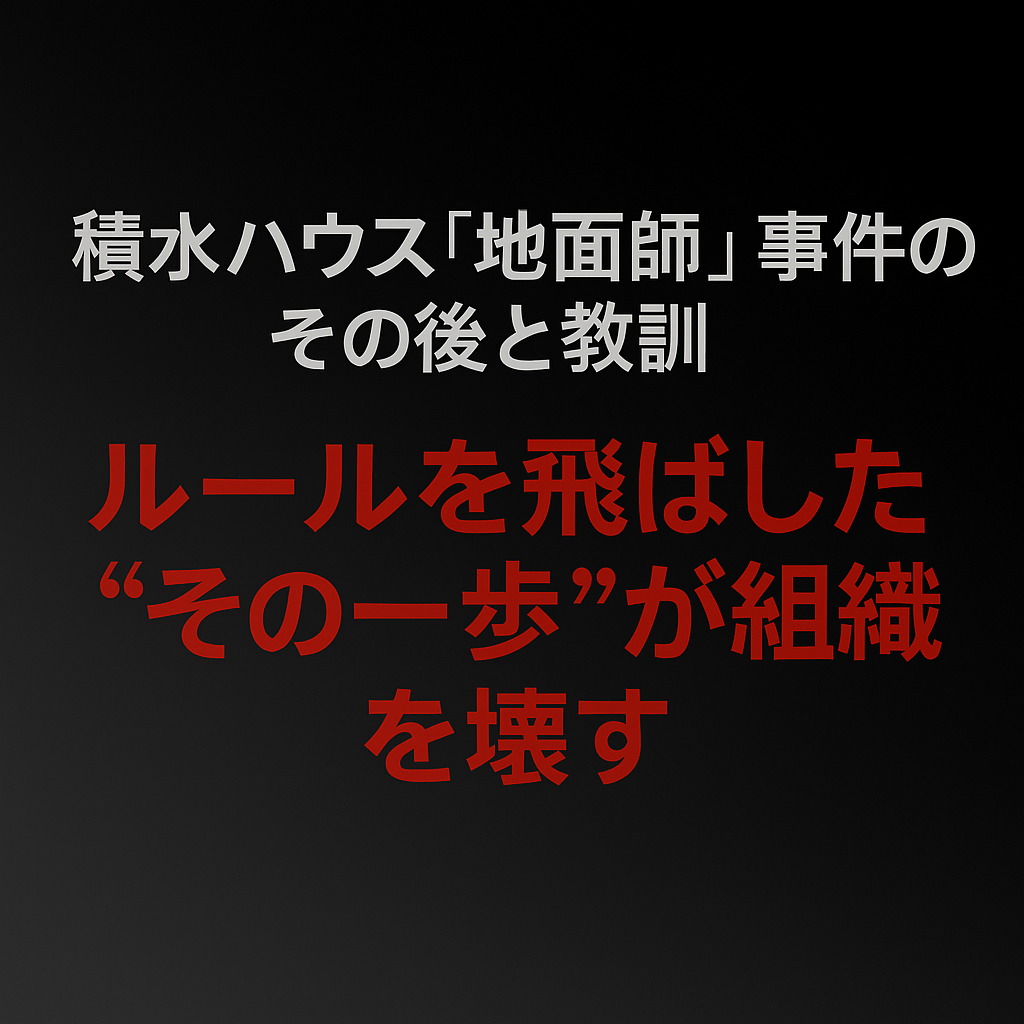【最新記事の目次】
積水ハウス「地面師」事件のその後と教訓──ルールを飛ばした“その一歩”が組織を壊す
こんにちは、森友です。
Netflixで放映された「地面師たち」で一気に注目された事件から学べる、一会社員としての教訓と真相に迫ります。
2017年、大手住宅メーカーの積水ハウスが55億円を騙し取られるという、かつてない不動産詐欺事件が起きました。
「そんな巨額詐欺、自分の会社には関係ない」と思った方も多いかもしれません。けれど、実はこの事件の核心にあるのは「地面師」ではなく、社内で“ルールを飛ばした”判断だったのです。
そしてそれは、現場で意思決定を任される現場マネージャーにも起こりうる話──。
この記事では、事件の概要だけでなく、その後の社内抗争、責任の所在、そして私たちが現場でどう生かせるかまで、わかりやすく整理してお伝えします。
Netflixオリジナルドラマ『地面師たち』は、
第1章|大企業が55億円騙された日──「海喜館」詐欺の全貌
舞台は、東京都品川区の一等地。かつて老舗旅館「海喜館」があった約600坪の土地に、積水ハウスが目をつけました。
この土地を巡り、「所有者」と名乗る人物たちが登場。提示された書類は完璧で、パスポート・印鑑証明・登記情報すべてに不審な点は見つからなかったと言います。
積水ハウスは早急に契約を進め、約70億円の土地取引のうち、55億5000万円を先に支払ってしまいます。
しかし後日、驚愕の事実が発覚──
- 登場していた「所有者」は完全な偽物
- 印鑑証明も登記書類もすべて偽造
- 背後には詐欺集団「地面師グループ」が存在していた
この事件は「積水ハウスが詐欺に遭った」として大々的に報道され、日本中を驚かせました。
けれど本当に恐ろしいのは、ここからです──。
第2章|社内で何が起きていたのか?──正規ルートを飛ばした“焦りの一手”

積水ハウスほどの大企業であれば、本来こうした不動産取引には慎重な社内手続きが存在します。
・法務部門による契約書の精査
・登記簿や所有者確認の徹底
・取締役会の決裁ルート
しかしこの事件では、現場主導で手続きが“すり抜ける”ように進行していたのです。
なぜそんなことが起きたのでしょうか?
背景には、次のような「焦り」があったとされています。
- 希少な都心の一等地で、競合他社も狙っている
- 少しでも早く契約を押さえたいという営業現場のプレッシャー
- 所有者(を装う人物)との交渉期限がタイトだった
このような状況の中で、社内のチェック機構や、冷静な判断を促す意見が「邪魔なもの」として処理されていきました。
法務担当の“慎重な姿勢”が煙たがられ、「スピード重視」の空気が勝ってしまったのです。
結果として、社内承認を待たずに先に契約・送金が進められ、誰も止められない状態になっていました。
ここで起きていたのは、決して特殊なことではありません。
「面倒なプロセスを飛ばした方が早い」「うちのチームだけは大丈夫」──。
その一歩が、やがて組織全体の信頼を壊すことになるのです。
第3章|詐欺より深刻だった、社内抗争の始まり
事件発覚後、積水ハウス社内は混乱に包まれました。
取引に関わった担当部門の責任が問われる一方で、経営トップの責任をどうするかが焦点となったのです。
このとき、事態を重く見たのが当時の会長・和田勇氏。
彼は「社長・阿部俊則氏の責任は重大だ」とし、2018年1月、取締役会において社長の解任動議を提出します。
しかしこの動きは否決。
すると今度は、阿部社長が逆に和田会長の解任動議を出し、こちらは可決──
会長が辞任に追い込まれるという異例の展開となりました。
この一連のやりとりは、メディアから「積水ハウス・クーデター劇」と報じられ、経営陣の分裂が白日のもとにさらされました。
さらに問題を深めたのは、次のような視点です。
- 社内の責任追及が、権力闘争にすり替えられた
- 株主への説明責任や、再発防止の姿勢が曖昧になった
- 「結局、誰も責任を取らなかった」という印象が広がった
この社内抗争により、積水ハウスは「地面師に騙された会社」から、「組織としてのガバナンスに問題がある会社」として見られるようになります。
被害額以上に、企業としての信頼とイメージを失った──これが“本当の損失”だったのかもしれません。
第4章|これは“隠蔽体質”の結果だった──声を上げた人が、消された現実
積水ハウスの社内では、この取引に対して「おかしい」と感じた社員が実際に存在していました。
契約書類の整合性、所有者との連絡状況、現地でのやりとり──
少し冷静に見れば違和感があるという声は、法務や管理部門の一部から上がっていたのです。
けれど、その声は“届きません”でした。
・「もう決裁が通っているから」
・「現場が押さえにかかってるから止められない」
・「上がGOを出したんだから口を出すな」
──そんな空気が、問題提起を“潰す”ように社内を覆っていたのです。
これは、詐欺に遭ったこと以上に深刻な問題でした。
なぜなら、こうした「おかしいと言えない空気」がある限り、どれだけ立派なルールや仕組みがあっても、形骸化してしまうからです。
・誰かが気づいても止められない
・言った人が損をする
・面倒を避けたいから黙っておく
──そんな体質こそが、55億円の損失と、企業全体の信頼失墜を招いた根本要因だったのではないでしょうか。
隠蔽というのは、情報を隠すことではなく、「耳をふさぐ」ことから始まる。
積水ハウス事件は、私たちにそのことを強く突きつけています。
第5章|なぜ“他人事ではない”のか?──私たちの現場にもある危うさ

この事件は、「大企業が55億円も騙された」という話では終わりません。
もっと大事なのは──
“ルールを飛ばす”判断は、どんな現場でも起きうるということです。
たとえば、こんな場面を想像してみてください。
上司に相談すべきか迷ったが、「面倒だし、自分で進めよう」と判断した
正式な承認を通さず、LINEや口頭で済ませた
時間がないからと確認を省略し、勘に頼った
こうした判断は、日常的に誰でもしていることかもしれません。
けれどそれが積み重なった先に、取り返しのつかない損失や信頼の崩壊が待っているとしたら──?
積水ハウスの件は、私たちが現場で抱えるジレンマや判断ミスが、どう組織を揺るがすかをリアルに教えてくれます。
「今すぐ欲しい成果」と、「あとで守れる信頼」──
そのどちらを選ぶかは、現場の判断に委ねられています。
だからこそ、私たちはこう自問する必要があるのです。
「ルールは誰のためにあるのか?」
「私の判断が、未来のチームを守るのか?」
結び|ルールは“縛る”ものじゃない。“守るべき未来”を守るもの。
積水ハウス事件の本質は、単なる詐欺被害ではありません。
・確認プロセスを飛ばしたこと
・慎重な声を封じたこと
・社内の権力争い
──それら一つひとつが、「組織としての信頼」をじわじわと壊していったのです。
ルールは、時に面倒です。時間もかかるし、上司に説明するのが億劫なこともあるでしょう。
けれど、ルールは“縛る”ためにあるのではなく、“未来を守る”ためにある。
正しいルートを踏むこと、確認を怠らないこと、違和感を放置しないこと──
それらはすべて、「あとから自分を、仲間を、会社を守るため」の保険なのです。
積水ハウスの事件は、遠くの話ではありません。
問題の大小はあれど、あなたの職場でも、すでに似た構造が始まっているかもしれない。
そう思えるかどうかが、リーダーとしての感度であり、責任なのだと思います。