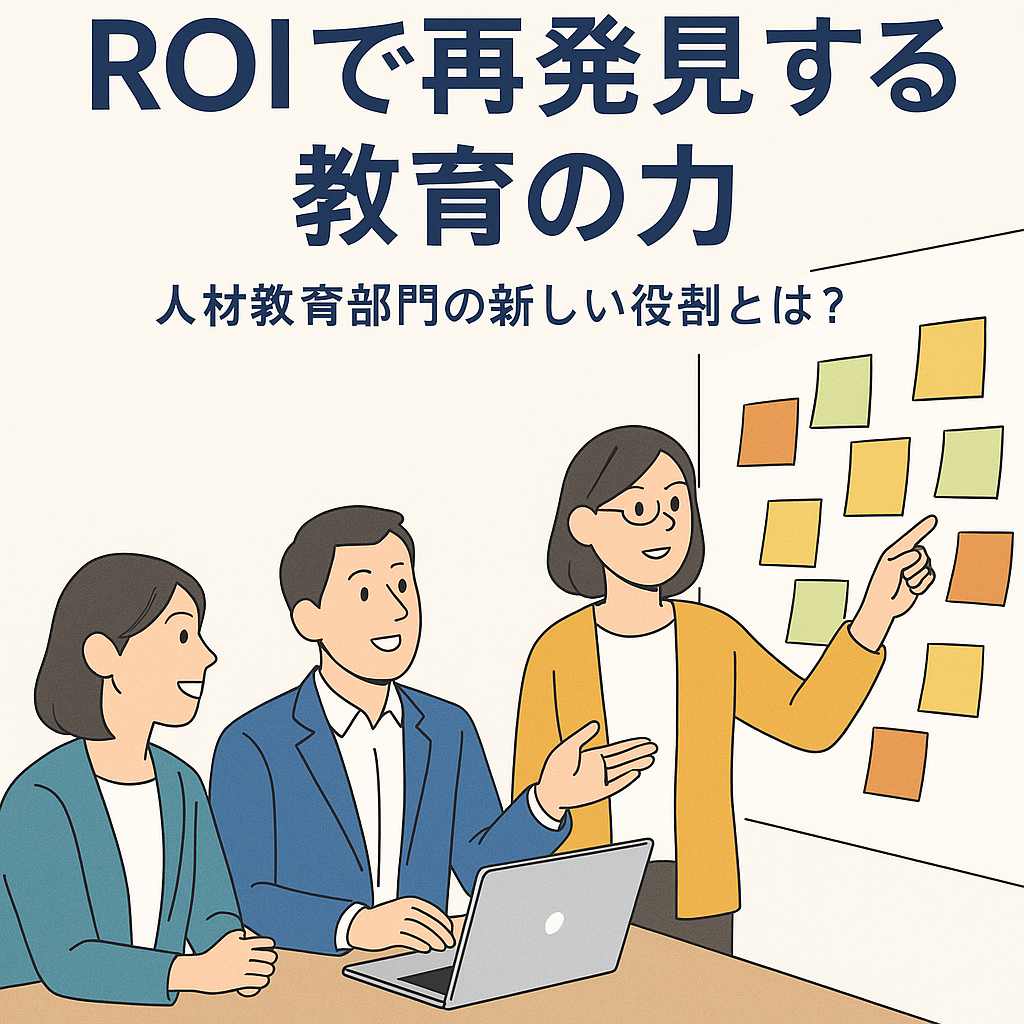【最新記事の目次】
ROIで再発見する教育の力|人材教育部門の新しい役割とは?
こんにちは!森友です。
私たちは、日本を代表する小売業として、1万人規模の社員研修を自前で企画・設計し、運営から講師まで一貫して担っています。
新人研修、階層別教育、マネジメント研修、チェーンストア理論研修など——
人材教育部門として、社員一人ひとりの成長を支える学びの場をつくってきました。
ここ数年の成果は革命的で、若手社員の離職率の大幅低下、定着率の向上、現場の活性化。
直接見えにくいところではありますが、
私たちの取り組みは、会社の“土台”を静かに支えてきたと感じています。
ただ最近は、トップからこんな声をいただくようになりました。
「で、何が変わったのか?」「どの数字に表れているのか?」
この問いにどう応えるか——
上記に書いた若手社員の離職率の大幅低下などは示せていますが、低下した上で今の教育をどう進化させていくか、少し真面目に考えてみたことを、
今日は気軽に読んでもらえたらうれしいです。
私たちは、教育に関してどんな要望にも柔軟に応えられ、
そのうえで最大の効果を出せる、プロ集団だと信じています。
トップからの突然の問いに思う事

今、私たち人材教育部門には、新たな問いが投げかけられています。
「この教育は、どれだけ会社の成果につながっているのか?」
良くなった今、環境は大きく変化しようとしています。
企業が持続的に成長していくためには、教育の力を“成果”へとつなげる視点が、これまで以上に求められるタイミングかもしれません。
ROI(教育投資対効果)という言葉が、教育部門にとっても他人事ではなくなった今、私たちは新しい役割を果たすタイミングに差しかかっています。
「やめるか、続けるか」ではありません。
「どう進化させていくか」。この問いに向き合うべき時なのです。
本稿では、OFF-JT教育を継続しながらも、経営成果に直結する“次の一手”をどう打つかを一緒に考えていきます。
なぜ今、教育部門は変わるべきか
環境変化は待ってくれません。
DXの波、人口減少、市場競争の激化。
すべてが企業に、より早く、より確実な成果を求めています。
人材教育に対しても、もはや「やったかどうか」ではなく、
「どれだけ会社の売上・利益に貢献したか」が問われる時代になりました。
教育部門がこの変化に応えなければ、存在意義を問われるのは、もはや時間の問題です。
守るべきは「形式」ではない。
未来をつくる力としての教育です。
現状の問題提起:会社全体の教育の質をコントロールできているか?
一度、自問しましょう。
各部門に存在する教育担当者たち。
彼ら自身への「教育」は、誰が責任を持って行っていますか?
現場に任せきりではないですか?
教え方も、意識も、バラバラ。
成果も人によってまちまち。
それは本当に、教育部門がコントロールできている状態と言えるでしょうか?
「教える側」を育てる。
この視点を欠いたままでは、いくら研修を打っても、成果が全社に広がることはありません。
ROIに貢献する教育設計とは
これからの教育部門の使命は明確です。
ROI(教育投資対効果)を生み出す教育に進化すること。
つまり、
- 客単価を上げる
- 粗利益率を高める
- 離職率を下げる
- 生産性を上げる
これら会社の「経営指標」に直結する教育テーマに切り替えなければなりません。
単なる「知識付与」ではない。
「行動を変え、結果を変える」教育。
それが、これからの教育部門に求められている使命のように私は思います。
今のOFF-JT教育をやめたらどうなるか?(メリット・デメリット)

メリット
- コスト削減(研修開催費、教材作成費)
- 人材教育部門の人員を別部署に移行できる
- 現場OJTにリソース集中
- フレキシブルな現場対応ができる
デメリット
- 教育の質の標準化が崩れ、それぞれの部門教育に偏る可能性。
- 中長期の人材力低下(体系的な育成ができない)
- 企業理念・行動規範の継承が薄れる(個展経営になるやすくなる)
- 若手の離職率が大きく上昇するリスク
たしかに短期的にはコストが浮くかもしれません。
しかし、失う未来の方が、はるかに大きい。
やめるべきではない。
進化させるべきなのです。
教育部門のチェンジにチャレンジする
今のOFF-JT教育にも確かな意味があります。
離職を防ぎ、モチベーションを保ち、企業文化を継承する。
それは誇るべき成果です。
誰よりも、私たち教育部門自身が、その価値を信じなければなりません。
しかし、それだけでは足りない。
時代は、変化を求めています。
トップの言うROI、経営成果への貢献。
それは単なる命令ではありません。
時代の要請なのです。
トップに言われたからではない。
未来をつくるために、自ら変わる。
今のOFF-JT教育を続ける承認をトップから得るためにすべきこと
① 教育の存在意義を説明する
- 離職率低下、定着率向上、企業文化継承という成果を数値で示す
② コスト対効果(ROI)視点で語る
- 売上・粗利益アップに寄与する研修設計
- 新人育成コスト削減、ミス削減などの効果を定量的に説明する
③ 改善提案もセットで出す
- 今後は成果測定を標準化する
- 時流に合わせたプログラムリニューアルを行う
- 部門教育担当者の育成にも乗り出す
④ トップ目線で語る
- 教育を続けること=企業の人的資本価値を高める=未来の成長力を確保する
- 「守るために進化する」という意志を示す
新たな挑戦:ROIを生み出すプログラムを導入する

今のOFF-JT教育をベースにしながら、
ROIを生み出す新しいプログラムを加える。
具体例
- 高単価販売力強化研修
- 顧客リピート率向上プログラム
- 店長・マネジャーの数字管理研修
- 生産性改善プロジェクト型研修
すべて、「売上・利益」に直結する教育テーマ。
これを教育部門から提案し、実装していく。
やるべきことはもう分かっている。
後は、行動するだけです。
まとめ|“教育のこれから”を、私たち自身の手で形にする
今、教育部門は大きな岐路に立っています。
トップから「やめろ」と言われているわけではありません。
けれど、“このままでいいのか”という問いは、私たち自身の中にも静かに芽生えているはずです。
OFF-JT教育は、これまで確かな成果を出してきました。
離職を防ぎ、モチベーションを高め、企業文化を継承してきた。
その価値は、私たち自身が一番よく知っています。
だからこそ、守るだけではなく、次の姿を描いていきたい。
ROIという視点で“成果につながる教育”へと、進化させていく。
それは、トップに言われて動くのではなく、
未来のために、私たち自身が選ぶ挑戦です。
今あるOFF-JTの価値を再発見し、さらに高めていくこと。
それが、教育部門としての「新しい役割」なのだと私は思います。
未来は、まだ白紙です。
どんな絵を描くかは、これからの私たち次第です。
例えば、このような講座です。
講師として研修に登壇するあなたが、自信をもって受講者に向き合えるように──。
このシリーズでは、講師としての“型”と“在り方”を、初級・中級・上級と3つのステップに分けて整理しました。