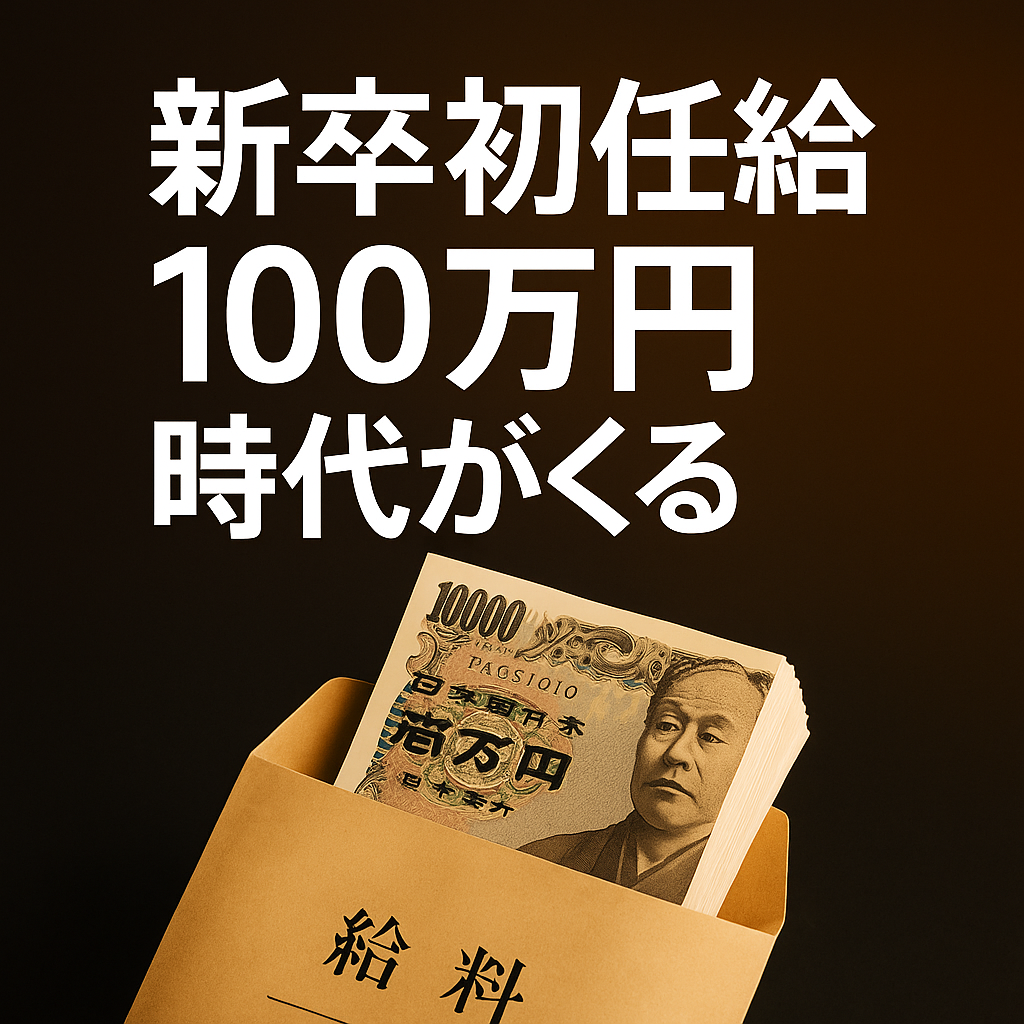【最新記事の目次】
1. 2050年、新卒初任給は100万円になるかもしれない
それが「夢物語」や「一部の大企業だけの話」だとは思いません。
むしろ、インフレが続くこれからの日本では、現実的な未来だと私は考えています。
たとえば──
- 1980年の大卒初任給:約12万円
- 2000年:約20万円
- 2025年:30万円前後
これまでの賃金の推移は緩やかだったとはいえ、今後はインフレ構造の中で給与の急上昇が進む可能性があります。
年2〜3%のインフレが続けば、25年後には物価は2倍以上。
100万円の初任給が“ようやく一人前”という時代が訪れるかもしれません。
2. デフレにはもう戻らない。その理由

かつてのように「価格が下がるのを待つ」「そのうち落ち着く」という前提では、これからの時代には対応できません。
今の日本は、すでに構造的なインフレに突入していると考えたほうが現実的です。
- 最低賃金は毎年上昇。企業が人件費を下げる余地はほぼない
- 円安・原材料高・輸入コストの高止まりが常態化している
- 値上げを前提にした価格設計を行う企業が急増している
- 政府・日銀が「物価上昇2%」を目標に動き続けている
このような現実を見れば、「デフレに戻る」どころか、価格は“戻らないもの”として前提にするべき時代に入ったと言えるのです。
3. インフレ構造の本質:お金の価値が“薄まる”
インフレとは、「モノの値段が上がる」というより、“お金の価値が薄まる”現象です。
同じ100万円でも、将来は今のように使えなくなる。
ここにおいて、得をするのは誰か?──
それは過去の価値でお金を借りた人・モノを買った人です。
たとえば、今3,000万円の住宅ローン(固定金利1.3%)を組んだとしましょう。
もし25年後、物価が2倍になっていたら、そのローンの実質的な負担はほぼ半分になっています。
これが、インフレの“裏の仕組み”です。
つまり、インフレ時代には、「借金は武器になる」「現金は目減りする」という感覚を持つことが非常に重要になります。
4. 借金は悪ではない。「武器」になる時代
インフレ下では、お金の価値が時間とともに下がっていく。
つまり、今のうちにお金を借りて、将来の“軽くなったお金”で返すというのは、理にかなった行動です。
■ 戦後の日本にあった“インフレ成功パターン”
高度経済成長期、住宅ローンを組んでマイホームを建てた家庭が数多くありました。
給料は毎年上がり、物価も上がり、でもローンの元本はそのまま──
結果的に「借金が軽くなった」のです。
■ 現代も、固定金利の借入は強い
たとえば、企業が設備投資や新店舗展開を固定金利ローンで行うとします。
将来の収益を生みながら、インフレによって借金の負担は相対的に減っていく。
これは、「現金を貯めているだけ」の企業では決して得られない恩恵です。
もちろん、無計画な借金はリスクになります。
でも、インフレを前提にした設計であれば、借金は“最大の守り”にもなるのです。
5. 経営感覚は「変化を読む力」から始まる
インフレ時代に突入した今、店長や現場責任者には新しい“経営感覚”が求められます。
私は、特にこの3つの視点が重要だと考えています。
(1)値上げを“怖がらず、正しく伝える”力
「値上げ=悪いこと」という時代は終わりました。
むしろ、「なぜ値上げするのか」「何を守るためか」をきちんと伝えることが、お客様の信頼につながります。
(2)借金を“未来の投資”としてとらえる感覚
現金を貯め込むよりも、仕組みづくり・教育・省人化投資に資金を回す方が、将来の利益を生みます。
借金=攻めではなく、生き残るための守りという視点が必要です。
(3)人件費の上昇を“利益構造”に変える設計力
人件費が上がることをコストではなく、生産性・定着率・ブランド力への投資と見なす。
マニュアル整備・標準化・新人教育の再設計が、生き残りの鍵になります。
価格が戻らない、賃金も戻らない──ならば、構造ごと変えていくこと。
それが、今の時代に求められる“経営感覚”です。
6. 個人としてどう備えるか?生き残る力とは
ここまで「インフレ時代の経営感覚」について述べてきましたが、個人としてどのように備えるかも、同じくらい重要です。
私はこう考えています。
■ 給料アップは“新卒だけの話”ではない
新卒初任給100万円──これは象徴的な変化に過ぎません。
インフレ下では、市場価値のある人材がより高く評価されるようになります。
つまり、スキルや実績を持つ人にとっては、さらに大きな報酬チャンスがあるということです。
■ 「生き残る会社」に属するのが最大の防御
インフレが進めば、企業間の二極化も進みます。
価格転嫁ができる企業、ブランド力のある企業、仕組みで回る企業──そうした会社は、むしろ強くなります。
逆に、値上げできない・人が辞める・仕組みが弱い会社は、苦しくなっていく。
個人として最も大切なのは、変化に適応できる組織に身を置くことです。
■ 自分の市場価値を高め続ける
「給料は会社がくれるおこづかい」ではありません。
それは自分が市場に提供した価値の対価です。
学び続ける人、仕組みを作れる人、人を育てられる人──
そういう人が、これからの時代のインフレ社会でも経済的にも精神的にも豊かになっていくのだと思います。
7. 未来は不安ではない。「備える人」が強いだけ
インフレは「恐ろしい変化」ではありません。
むしろ、時代のルールが書き換わる転換点です。
価格が上がる、給料が上がる、借金が軽くなる──それはすべて、“過去とは違うゲーム”が始まっているというサイン。
そのルールを知らないまま動かない人が損をし、備えて行動した人が生き残るだけのことです。
新卒初任給100万円時代が来る。
それを笑うか、備えるか。
時代を読む力と、変化に適応する行動力──
これからの現場や経営に本当に必要なのは、「勘」ではなく「構造を読む力」だと思っています。
関連記事
電気代が上がる。物流費が上がる。時給が上がる。仕入れも上がる──
値上げは「自分の店だけの問題」ではなく、「社会全体の流れ」になっているのです。
つまり今、店が向き合うべきなのは
「値上げをするかどうか」ではなく、「どう値上げするか」です。