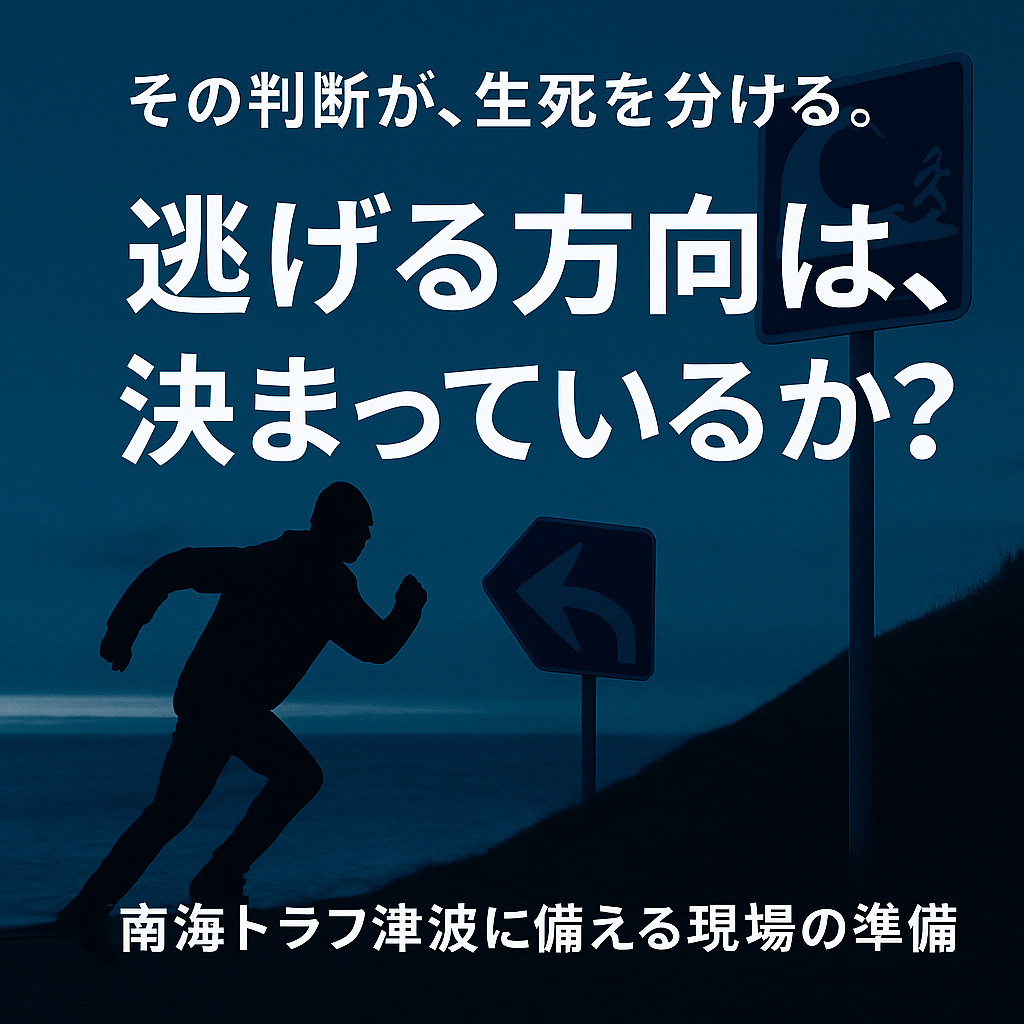【最新記事の目次】
“逃げる方向”は決まっているか?|南海トラフ津波に備える現場の準備
こんにちは、森友ゆうきです。
南海トラフ地震に備える上で、最も恐ろしいのは「津波」です。
建物の倒壊や火災、停電などももちろんリスクですが、津波は“逃げ遅れたら終わり”という圧倒的な破壊力を持っています。
揺れが収まってから避難を始めても、間に合わないかもしれない。
「判断の1分」が、「命の境界線」になる。
この記事では、店舗で働く店長・スタッフが“津波から命を守るためにできる備え”にフォーカスしてまとめます。
第1章:本当に津波対策を取れているか?──問い直すべき5つの視点
南海トラフ地震は、単なる「地震被害」ではありません。
最大の脅威は“その後に来る津波”です。
店長として、スタッフやお客様の命を守る責任がある中で、
次の問いに「YES」と自信を持って答えられるでしょうか?
- 店がある地域に「津波警報」が出たとき、何をするか決まっていますか?
- 建物が浸水した場合、避難する“高台”や“ルート”は明確ですか?
- アルバイトや外国人スタッフにも、避難行動が伝わっていますか?
- 深夜に震度6強以上が来たとき、店に行くの?行かないの?会社の指示・判断は?
- 定期的に「津波を想定した避難訓練」を実施していますか?
一つでも「うーん……」と迷ったなら、津波対策はまだ不十分です。
命を守る初動は、マニュアルではなく、店長の“即判断”にかかっています。
第2章:揺れが収まってからでは遅い──“津波の初動”は誰が出すのか?
大きな揺れが収まり、少しざわつく店内。
そのとき、「さて、次にどうするか」と考えていたら、もう遅いかもしれません。
津波は、地震の発生から数分〜十数分で到達します。
“揺れたらすぐに逃げる”という行動が、命を分ける決定的なポイントです。
ただし現実には──
- マニュアルが手元にない
- 本部からの連絡がまだ来ない
- 誰も避難の声を出していない
そんな空気の中、店長のひと声があるかどうかが運命を左右します。
「津波警報が出ています!外に避難しましょう!」
その声を、“誰よりも先に出せる人”が、命を守る現場リーダーなのです。
第3章:垂直避難か、屋外避難か──判断を分ける3つの基準

津波の危険が迫ったとき、「どこへ逃げるか」は決まっていますか?
実は、“逃げる方向”の判断こそが、生死を分ける最初の選択になります。
大きく分けて、避難方法には2つあります。
- 垂直避難:建物の3階以上など、高い場所へ上がる避難
- 屋外避難:徒歩で高台や津波避難ビル・避難所へ向かう避難
どちらを選ぶべきかは、次の3つの視点から判断する必要があります。
1. 店舗がある場所の「海抜」は何メートルか?
海に近い、海抜が低い場所では、揺れを感じた時点ですぐに避難判断を。
2. 建物は「垂直避難」に対応しているか?
3階以上がある、構造的に耐震性がある、屋上へ上がれる構造か。
これらがない建物では屋外避難一択になります。
3. 津波の到達時間は何分後か?
高台までの距離や、到達時間のシミュレーションを自治体ごとに確認しておくことが重要です。
「とりあえず外に出る」ではなく、「どこへどう逃げるか」が決まっているか。
それが現場の安心を生む、事前準備の真の価値です。
第4章:津波避難訓練を“現場視点”で組み立てる
南海トラフ地震の対策は、「知っている」だけでは不十分です。
実際に“動ける状態”を作っておくことこそ、現場にとっての本当の備えです。
そのために必要なのが、実際の店舗や立地に合わせた津波避難訓練です。
1. 「何分でどこまで逃げられるか」を体で確認する
地図上では近く見えても、実際に避難所まで歩いてみると意外と時間がかかる。
まずは現場チームで歩き、「現実的な避難時間」を把握することが重要です。
2. 誰が避難を呼びかけるかを明確にする
地震が発生してからの初動で迷わないよう、「声を出す担当」を決めておきます。
できれば、サブの担当も決めておくと、シフトによる不在リスクを減らせます。
3. 顧客への対応フレーズをあらかじめ共有しておく
「津波警報が出ています。こちらから避難しましょう」といった言葉を、
全スタッフが迷わず使えるよう、簡単な定型文を共有しておきましょう。
現場で“再現できる避難行動”にしておくこと。
その準備が、いざという時のパニックを防ぎ、命を守ることにつながります。
第5章:避難時に“何を持って逃げるか”は決まっているか?
津波から避難する際、最も大切なのは「とにかく早く逃げること」。
持ち出すものをその場で迷っていたら、命のリスクを高めてしまいます。
だからこそ、店舗ではあらかじめ“命を守るために最低限必要なもの”を準備しておく必要があります。
店長・スタッフが避難時に持ち出すべきもの(最小限)
- 携帯電話(連絡・情報確認のため)
- モバイルバッテリー(通信維持)
- スタッフ名簿・緊急連絡網(紙でも可)
- ホイッスル(笛)(助けを求める手段)
- 簡易応急セット(絆創膏・消毒・常備薬)
- 懐中電灯またはヘッドライト
- 500ml程度の水
店として備えておきたいこと
社員・スタッフの人数分、同じ中身の防災バッグを準備する。
できれば、スタッフルームや事務所の出入口付近に常備しておくと即持ち出せます。
なお、売上金・鍵類などは持ち出さないのが原則です。
非常時は、何よりもまず命の確保を優先する判断を共有しておきましょう。
補足:備えを具体化するために見直したい4つの視点
1. 店舗の「海抜」と津波想定区域を確認しているか?
お店の立地が津波の浸水想定区域にあるかどうかは、国土交通省の「重ねるハザードマップ」や、自治体の防災ページで確認できます。
地図上で住所を入力するだけで、海抜や津波の到達予測がわかります。
2. 店長不在時に“避難判断”をする人は決まっているか?
災害は、店長がいないときにも起こります。
誰が代行判断をするのか(サブリーダー)をシフト単位で決めておくと、判断の空白がなくなります。
3. 店舗の構造上、避難導線は明確になっているか?
スタッフルームからの出口が1箇所、売場とバックヤードがつながっていない…など、構造的な制限を事前に確認し、避難ルートを確保しておきましょう。
4. 接客中・レジ中の“判断”も共有しているか?
「お会計中だったらどうする?」「お客様が不安がっていたら?」
このような想定をスタッフ間で話しておくことで、本番で迷わず動ける心理的余裕が生まれます。
準備とは、物だけではなく「判断基準と心理の余白」を整えることでもあります。
まとめ:命を守るのは、日々の“判断力”
南海トラフ地震のような大災害は、「その日」がいつ来るかは分かりません。
だからこそ、日々の備えと、いざという時に“判断できる人”であることが、命を守る最大の力になります。
避難ルートは決まっているか?
誰が避難の声を出すのか?
何を持って逃げるのか?
この記事で触れた一つ一つを、明日ではなく今日から見直すこと。
それが、店で働く仲間を、お客様を、そして自分自身を守る一歩になります。
備えるのは、不安になるためではなく、「判断できる自分」であるため。
店長として、防災の責任者であると同時に、
「現場の命を預かるリーダー」であることを、どうか忘れないでください。