【最新記事の目次】
中国発ライブコマースの最前線|拼多多(ピンドゥオドゥオ)に学ぶ“その場で売れる”仕組みと日本の課題
こんにちは、森友です。
「ライブコマースって、なんかすごそう…でも、どうやれば売れるの?」
そう感じている方も多いのではないでしょうか。
私自身、はじめて中国のEC企業・拼多多(ピンドゥオドゥオ)のライブ配信を体験したとき、その“仕組みの完成度”に驚かされました。
商品を紹介しながら、視聴者の質問にリアルタイムで答える。
気に入ったら、画面内に出てきた購入ボタンをタップするだけ。
サイズやカラーもその場で選べて、買い物が配信中に完結するんです。
日本のライブ配信との違いは、まさに“売るための設計”がされているかどうか。
この記事では、拼多多のライブ販売の仕組みから、日本の小売が学べるヒントまで、具体的にお伝えします。
第1章|ライブ配信を「しているだけ」では売れない
最近、日本でもライブ配信を取り入れる会社が増えてきました。
でも、「見てはもらえるけど、あまり売れない」という声をよく聞きます。
その大きな理由のひとつが、「配信中に買えない」ということ。
気になる商品があっても、「後でECサイトで買ってくださいね」と言われるだけ。
視聴者はリンクを探し、検索し、カートに入れ…その間に気持ちは冷めてしまいます。
一方、拼多多(ピンドゥオドゥオ)のライブでは、
- 質問ができる
- その場で回答してくれる
- 「欲しい」と思った瞬間に購入ボタンが表示される
- そのまま画面内で購入が完了する
お客様の“買いたい熱”が一番高まった瞬間に、そのまま買ってもらえる設計。
ここが、日本のライブ配信と大きく違う点です。
第2章|拼多多(ピンドゥオドゥオ)ってどんな会社?
拼多多は、2015年に中国で生まれたEC企業です。
アリババや京東(JD.com)と並び、中国ECのトップクラスに成長しています。
その特徴は、「安さ」×「SNS」×「仕組み」。
短期間で何億人ものユーザーを獲得した理由を、3つに分けて紹介します。
1. SNSで広がる“共同購入”モデル
「誰かと一緒に買えば安くなる」
拼多多では、そんな仕組みで商品をシェア・拡散させています。
友人とグループを作って共同購入すれば割引になるため、
買い物が“ひとりごと”ではなく、“みんなごと”になるんです。
2. 地方の人々に特化した戦略
拼多多が注目したのは、大都市ではなく中国の地方都市や農村部。
この層に向けて、日用品や食料品をとにかく安く届けることに徹した結果、
今では中国全土にファンを持つ巨大プラットフォームになりました。
3. C2M(消費者直結型の生産)でムダを省く
消費者のデータを活かして、「今、売れそうな商品」だけをメーカーに作ってもらう。
これが拼多多のC2M(Consumer to Manufacturer)モデルです。
中間コストや在庫リスクを最小限にし、利益率とお客様満足を同時に追求しています。
第3章|ライブ販売に向いているのは“1点もの”——アウトレットこそ相性抜群

拼多多(ピンドゥオドゥオ)のライブ販売中の画面。視聴者のコメントがリアルタイムで流れ、商品はその場で購入可能な仕組みが整っている。
ライブ販売で特に相性がいいのが、アウトレット品・キズもの・展示品などの“1点もの”です。
たとえば:
- 家具:少しキズがある展示品のソファやテーブル
- 家電:開封済みや旧モデルなどの訳あり品
- アパレル:サイズやカラーが偏った残り在庫
こうした商品は、通常のECでは売れ残りがちですが、
ライブでリアルに見せながら説明すると、売れ方がまったく変わります。
「ここにキズがありますが、使う分には問題ありません」
「ラスト1点、今だけこの価格です」
そんな説明を聞いた視聴者は、納得し、即決します。
希少性・納得感・スピード感。
この3つがそろうライブ販売は、“売れ残り”を“売れ筋”に変える力を持っています。
第4章|“その場で買える”UXが、売上を変える
ライブ配信って、「話す」ことが大事と思われがちですが、
実はもっと重要なのが、“買える設計”ができているかどうかです。
日本の多くのライブ配信では、商品を紹介し終えたあとにこう言います。
- 「詳しくはECサイトでご覧ください」
- 「購入は後ほど、公式ホームページからお願いします」
これだと、せっかく興味を持ったお客様も、
別ページへ移動する間に気持ちが冷めてしまいます。
拼多多のすごさは、“その場で買えること”
私が体験した拼多多(ピンドゥオドゥオ)のライブ販売では、
- 気になる商品にその場で質問ができる
- すぐに返事が返ってくる
- 納得した瞬間に、画面に購入ボタンが出てくる
- その場でサイズやカラーも選べる
つまり、すべてが配信画面の中で完結しているのです。
「今ほしい!」という熱量が高まったその瞬間に、
迷わず買えるように設計されている。
これは、お客様の心理をとてもよく考えた仕組みです。
UXが売上を左右する時代へ
「いい商品なんだけど、あとで見るね」
——こう言われたお客様が、あとで戻ってくる確率は、実はかなり低い。
だからこそ、「今この場で買ってもらうにはどうすればいいか?」を考える必要があります。
UX(ユーザー体験)とは、お客様が商品に出会ってから購入までに感じるすべての“流れ”のこと。
拼多多は、その流れを丁寧にデザインしているから、ライブ配信で次々と商品が売れていくのです。
ライブ配信が売上につながらないと悩んでいる企業は、
話し方よりもまず、「買える導線があるか?」を見直してみてください。
第5章|ライブ販売は“現場任せ”にしない——本部が動く仕組みに変える
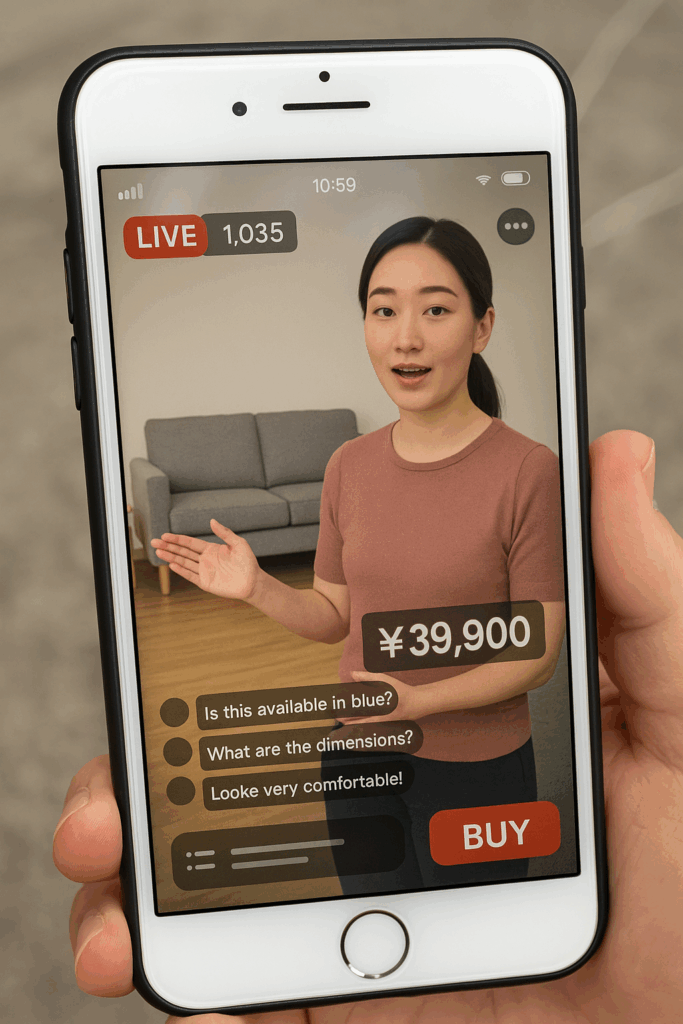
ライブ販売を始めよう!…そう意気込んでも、
「配信は店舗スタッフにおまかせ」ではうまくいきません。
たまたま話がうまいスタッフが売れたとしても、それは一時的な偶然。
本部が戦略を持って仕組みをつくる。
それが、ライブ販売を“再現できる成功”に変えるカギです。
現場に全部を背負わせない
現場スタッフにとって、
ライブ配信は「やったことのない仕事」であり、
「他の業務と並行するのが大変な負担」でもあります。
だからこそ、本部がやるべきことは:
- 台本の作成(話す順番・ポイント)
- 商品選定と特別価格の設定
- 撮影の段取りとサポート体制
店舗は“出演者”に専念できるよう、全体を設計してあげることが大切です。
ライブ向きな人材は“別枠”で配置する
すべてのスタッフがライブに向いているわけではありません。
むしろ、「カメラ慣れしている」「話すのが好き」「表現力がある」など、
ライブ販売に適した人材を見つけて、会社として活かす戦略が必要です。
現場に偶然いるのを待つのではなく、
ライブ専任メンバーを本部で育てていく視点が求められます。
第6章|日本の小売が学ぶべき3つの戦略視点
1. ライブ中に“買える設計”を持つ
ライブ配信で話すだけでは売れません。
買いたいと思ったときに、すぐに買える仕組みがあるかどうか。
購入ボタン・サイズ選択・決済完了まで、画面内で完結する導線があるかが分かれ目です。
2. 在庫を“ライブ向け商品”として見直す
売れ残り・展示品・訳あり在庫…
これらを「処分品」ではなく、“今だけ1点限りのライブ限定商品”として再提案する視点が重要です。
3. IT投資を先送りしない
ライブコマースは、コロナ禍で中国が一気に進めた分野。
拼多多(ピンドゥオドゥオ)をはじめとした企業が、「接客」ではなく「仕組みづくり」で成功しました。
日本でも、いずれこの波は必ずやってきます。
そのときに慌てないよう、今のうちからIT投資や社内での実験を進めるべきです。
第7章|まとめ──ライブ販売は“売れる仕組み”を作った者勝ち
ライブ販売で成功している企業は、声が大きいからでも、スタッフが芸人みたいだからでもありません。
売れる流れを設計しているか。
そこに尽きます。
拼多多(ピンドゥオドゥオ)はそれを、
商品選定、在庫連動、UX設計、人材配置まで含めて仕組みにしてきました。
これからライブ販売を取り入れる企業も、
「やってみよう」から一歩進んで、「どう仕組み化するか」を考えていくことが大切です。
森友の視点|ライブ販売が当たり前になった時、“お店”は何をする場所になるのか?
拼多多(ピンドゥオドゥオ)のライブ販売を体験して、私は強く感じました。
「質問して、納得して、その場で買える」体験は、間違いなくこれからの標準になります。
そうなったとき、私たちはこう問い直すことになるはずです。
—— お客様は、何のために“お店”に足を運ぶのか?
これからの店舗は、「商品を売る場所」ではなく、
「体験を届ける場所」「人とつながる場所」に変わっていくでしょう。
- 商品に実際に触れられる
- スタッフと会話できる安心感
- リアルだからこそ伝わる空気や臨場感
情報も、価格も、購入も、スマホで完結する時代。
「わざわざ行く価値」を作ることが、お店の新しい役割になっていきます。
ライブコマースが進む中で、お店の未来をどう描いていくのか。
それこそが、これからの店長や本部に求められる視点だと、私は思います。
2025年5月11日|森友ゆうき







