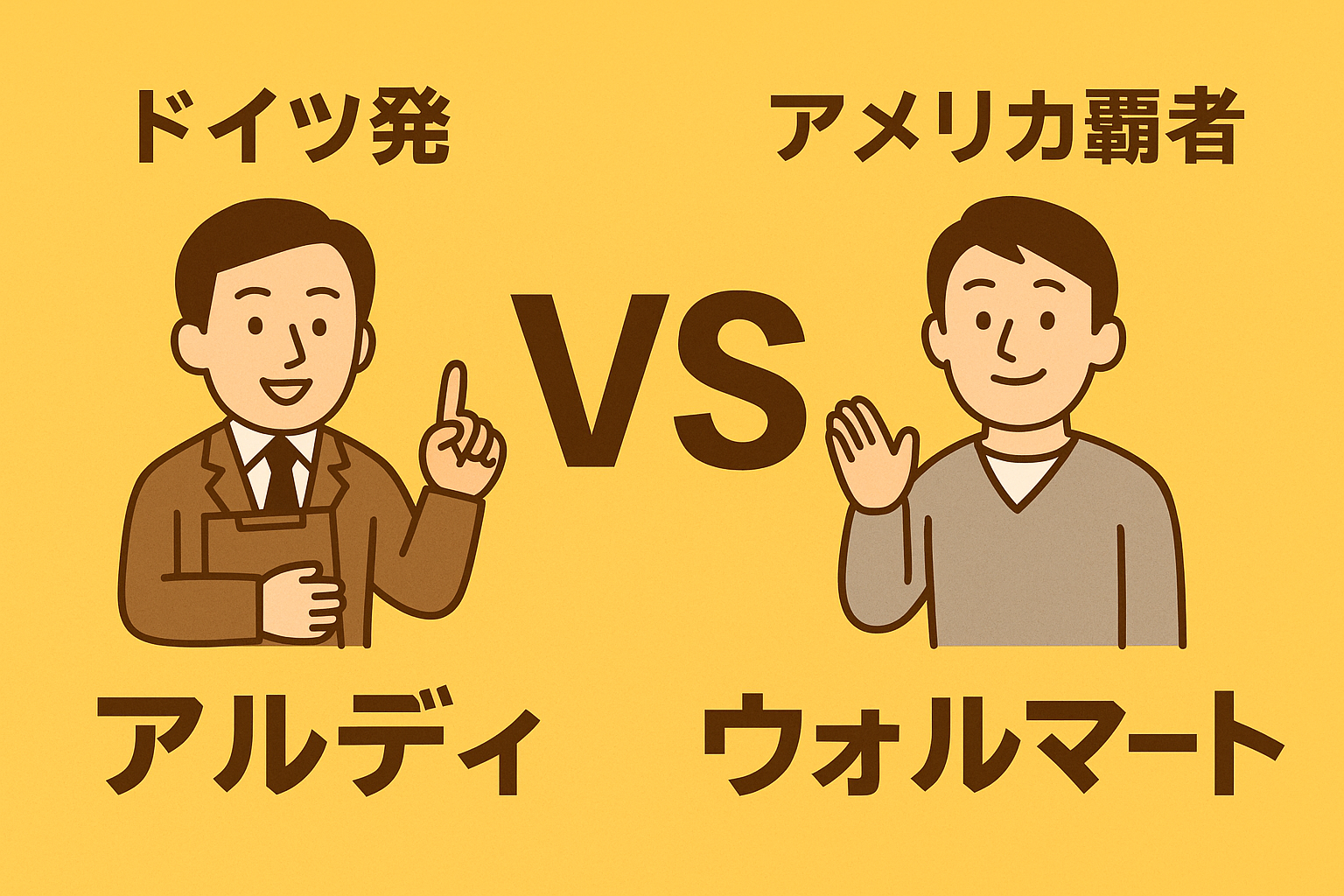【最新記事の目次】
アルディvsウォルマート|真逆の小売戦略に学ぶ現場改善のヒント
こんにちは!森友ゆうきです。
あなたは「ALDI(アルディ)」というスーパーをご存じですか?
ヨーロッパでは爆発的な人気を誇り、今や世界20カ国以上に12,000店舗以上を展開するグローバルなディスカウントストアです。
日本ではまだあまり知られていませんが、実はこのアルディ、
店舗マネジメントや現場運営を見直す上でヒントの宝庫なんです。
この記事では、そんなアルディの「仕組み化された運営」から、
日本の店長が現場に活かせる考え方をまとめてみました。
はじめに|ALDI(アルディ)とは?

ダイヤモンド チェーンストアより画像引用
アルディは1913年にドイツ・エッセンで創業された、世界有数のディスカウントスーパーチェーンです。
1960年代に経営方針の違いから、北部の「Aldi Nord(アルディ・ノルト)」と、南部の「Aldi Süd(アルディ・ズュート)」に分裂。現在は別企業として運営されています。
- グループ合計で世界20か国以上に約12,000店舗を展開
- アメリカではAldi Südが「ALDI」、Aldi Nordは「Trader Joe’s」として展開
- 欧州ではイギリス、フランス、スペインなどを中心に急拡大
アルディは「選択肢を絞ることで、迷わせず、安く、効率的に」という哲学を徹底しており、
“現場を人でなく仕組みで動かす”モデルとしても非常に参考になります。
ちなみに、アメリカで人気のTrader Joe's(トレーダージョーズ)も、実はアルディと深い関係があります。
その魅力と独自戦略については、また別記事でじっくりご紹介します。
アルディとウォルマートの運営戦略の違い
両社比較表
店舗数はアルディに軍配ですが、規模と扱い品目に大きな違いがあります。
どちらが優れているというよりも、「徹底的に絞る(アルディ) vs. 圧倒的に揃える(ウォルマート)」
という戦略の軸がまったく違うのがわかります。

アルディを語る上での6つの特徴
第1章|陳列は「並べない」パレット方式
アルディの売場では、商品が段ボールやパレットごとそのまま陳列されます。
補充のたびに並べ直す必要がなく、陳列時間を大幅に短縮。スタッフの省人化と作業の標準化が実現しています。
第2章|SKU数は最小限。商品数は約1500点
アルディは商品数を徹底的に絞っています。これは在庫管理、棚割、発注の複雑さを排除するため。
結果、店内導線も短く済み、買い物時間の短縮にもつながります。
第3章|PB比率90%以上。品質と利益の両立
ほとんどの商品が自社ブランド。品質は高く価格は安い――この構造により、顧客満足度と粗利を同時に成立させています。
売場の“迷い”を無くすという意味でも、SKUの最適化は注目ポイントです。
第4章|広告しない。価格と実力で勝負
CMやチラシなどの広告は最小限。口コミとリピーター獲得を重視した運営です。
余計なコストを省き、価格に還元する。この考え方は価格競争の激しい業界でも有効です。
第5章|作業の一部を顧客に設計する
レジ袋は有料。袋詰めはセルフ。レジ処理は超高速で、会計後は別スペースで袋詰めを行います。
これは「客の行動」をも含めてオペレーションをデザインしている好例です。
第6章|すべて直営。フランチャイズに頼らない管理
店舗はすべて本部直営で、売場・価格・販促までブレがありません。
統制と標準化のバランスが取れた運営は、日本のチェーン運営にも示唆が多いです。
まとめ|「人」ではなく「仕組み」で回す考え方
アルディのように、店舗運営を仕組みで支える発想は、日本の小売にも多く応用できます。
仕組みとは「人を楽にする」「誰がやっても同じ成果が出る」こと。
チェーンストアの成否は、現場を“感覚”で回すことではなく、“再現性ある仕組み”をつくることです。
今日はアルディを取り上げました。
チェーンストア企業で働くあなたの知識の一助になれば幸いです。
関連記事
マレーシア発のホームセンター「MR.DIY」は、いまや東南アジアを中心に世界中で4,000店舗以上を展開する急成長企業です。
その人気の背景には、単なる「安さ」だけでない、売場設計やブランド戦略の巧みさがありました。